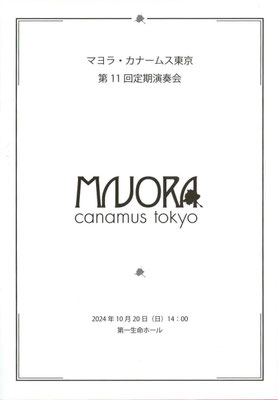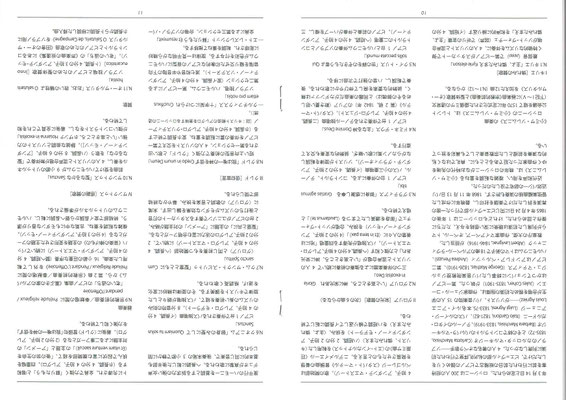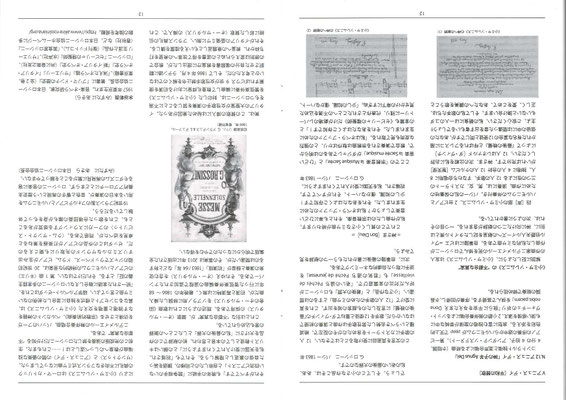- ホーム
- NEWS
- ロッシーニについて
- 日本ロッシーニ協会
- 協会の活動
- 例会の記録
- ロッシニアーナ
- 演奏会と動画
- メールマガジン
- 会長:水谷彰良
- オペラの作品解説
- オペラ以外の作品解説
- 小ミサ・ソレムニス(1)解説
- 小ミサ・ソレムニス(2)資料
- 研究・論文・論考(1)
- 研究・論文・論考(2)
- 書簡とドキュメント
- その他の自筆資料
- 19世紀の資料と文献
- ロッシーニ生涯と作品(1)
- 筆写譜と印刷譜
- ロッシーニ図像学
- 図像学(歌手ほか)
- 日本の受容と上演史
- 大正~昭和初期の楽譜
- 美食家ロッシーニ
- ロッシーニ全集ほか
- ロッシーニ研究所紀要
- ロッシーニ音楽祭
- インタビュー等
- ソフトとディスク
- オペラ楽譜の文化史
- 没後150年記念展示
- チェネレントラ展示2021
- ベッリーニ展示2024
- ウィリアム・テル展示2024
- セビリアの理髪師展示2025
- ファンのお宝グッズ
- ロッシーニ切手蒐集
- ロッシーニ時代の作曲家と作品
- 特設:泥棒かささぎ
- 入会案内/お問合せ
- 特設:知るサリエーリ
- 見るサリエーリ
- 聴くサリエーリ
- 映像のサリエーリ
- 日本のサリエーリ演奏
- サリエーリ2025
- サリエーリ拾遺
- オルフェーオの物語
ロッシーニ《小ミサ・ソレムニス》作品解説
ロッシーニの小ミサ・ソレムニス[小荘厳ミサ曲](1)作品解説のページです。著作権は著者・水谷彰良に帰属し、無断転載を禁じます。事前にこのサイトのお問合せフォームからご連絡ください。
更新記録 2025年10月30日 ── この頁を設置・公開しました
小ミサ・ソレムニス(1)
・小ミサ・ソレムニス(Petite Messe solennelle)作品解説
↑
日本ロッシーニ協会紀要『ロッシニアーナ』第38号(2018年6月発行)に掲載したオリジナル編成と管弦楽伴奏版の最も詳
しい作品解説──水谷彰良「ロッシーニ全作品事典 (37)《小ミサ・ソレムニス》」──の書式変更版です。
(2021年10月改訂)
ロッシーニ宗教音楽の傑作《小ミサ・ソレムニス》 水谷彰良
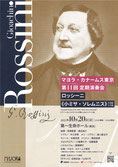
次に掲載するのは2024年10月20日にマヨラ・カナームス東京の第11回定期演奏会で演奏されたロッシーニ《小ミサ・ソレムニス》(ピアノ2台とハルモニウム伴奏によるオリジナル版)プログラムに掲載された作品解説:水谷彰良「ロッシーニの宗教音楽の傑作《小ミサ・ソレムニス》」です。管弦楽伴奏版の作品解説はその後に掲載します。
2024年10月20日、第一生命ホール マヨラ・カナームス東京《小ミサ・ソレムニス》
指揮/音楽監督:渡辺祐介、ソプラノ:中江早希、メゾ・ソプラノ:山下裕賀、テノール:中嶋克彦、バ
リトン:黒田祐貴、フォルテピアノ:小倉貴久子、加藤美季、ハルモニウム:高橋博子、合唱:マヨラ・
カナームス東京
2024年10月20日マヨラ・カナームス東京 ロッシーニ《小ミサ・ソレムニス》のプログラム表紙と作品解説のページ

ロッシーニ宗教音楽の傑作《小ミサ・ソレムニス》 水谷彰良
作曲家ロッシーニの歩みと《小ミサ・ソレムニス》の誕生
モーツァルトの死から2か月半後の1792年2月29日、ジョアキーノ・ロッシーニ(Gioachino Rossini, 1792-1868)はアドリア海に面した中部イタリアのペーザロで生まれた。14歳でボローニャの音楽学校に入学し、16歳で作曲した6曲の弦楽四重奏曲により早熟な才能を現した彼は、最初の歌劇《結婚手形》を18歳で作曲した。オペラ作曲家としての活動は1810年から29年までの20年間。全39作のうち《セミラーミデ》までの34作がベートーヴェンの交響曲第6番と第9番の間に書かれたことでも分かるように後期古典派に属するが、フランス王家の求めで1825年に活動の拠点をパリに移し、1829年にパリのオペラ座で初演した《ギヨーム・テル》が最後の歌劇となった。その原因は1830年の七月革命でシャルル10世が退位し、旧王家との契約が無効となったことにある。すでに始まっていた終身年金の支給継続を求めて裁判に訴えたロッシーニは、オペラの筆を折ったと公言し、サロン音楽家としてパリにとどまった。勝訴して帰国しボローニャで引退生活に入ったのは1836年、44歳のとき。母校の名誉校長に就任し、パリで最も美しいと言われた裏社交界[ドゥミ=モンド]の高級娼婦オランプ・ペリシエを二人目の妻に迎えた彼は、悠々自適の余生を送ることにした。
これで忘れられても不思議はないけれど、ロッシーニには栄光に満ちた晩年があった。1855年フランスに舞い戻り、1868年に没するまで13年間パリで新たな脚光を浴びるのだ。きっかけは、健康を取り戻した彼が1858年12月から私邸で始めた音楽の夜会にあった。創作意欲が蘇り、後に「老いの過ち」としてまとめられるピアノ曲と室内声楽曲を150ほど作曲し、夜会で披露したのである。美食家でもある彼は《ロマンティックな挽肉》《バター》《アンチョビ》《干しぶどう》と題したピアノ曲、《痙攣前奏曲》《喘息練習曲》《深い眠り~びっくりして眼を覚ます》などの風変わりなタイトルの曲を連作し、人気を博したのである。

演奏時間が80分に及ぶ《小ミサ・ソレムニス》も、「老いの過ち」のための小品から派生した名作である。1862年5月に脱稿した合唱曲〈八声とピアノフォルテのためのキリエ Chirie per otto sole voci e pianoforte〉がその発端で、全集版の校訂者ダヴィデ・ダオルミは〈クリステ・エレイソン〉がルイ・ニデルメイエール(Abraham Louis Niedermeyer, 1802-1861)作曲《荘厳ミサ曲 Messe solennelle》(1849年)の無伴奏合唱曲〈エト・インカルナトゥス Et incarnatus〉の転写であることから、前年亡くなった友人の作曲家へのオマージュと推測する。翌年〈キリエ〉に続く〈グロリア〉と〈クレド〉を作曲したロッシーニは、4人のソリストと混声合唱、ピアノのための《小さなグロリア・ミサ Piccola messa di Gloria》に再編し(1863年6月10日完成)、伴奏にパリのドバン社が特許を持つハルモニウム「アルモニコルド Harmonicord」を加える改作も施した。
そこに舞い込んだのが、フランス銀行頭取アレクシス・ピエ=ヴィル伯爵がパリのモンセー通りに建築する大邸宅の落成祝いの作品依頼だった。パトロンの求めを断れぬロッシーニは〈サンクトゥス〉と〈アニュス・デイ〉を作曲して荘厳ミサの体裁を整えるとともに、稽古の段階で旧作のピアノ曲《宗教的前奏曲》を挿入し、第二ピアノのパートを追加作曲して《小ミサ・ソレムニス[小さな荘厳ミサ曲]Petite Messe Solennelle》を完成させたのだった。
初演はニデルメイエール3年目の命日に当たる1864年 3月14日と定められた。ロッシーニは200人の招待客を前に行われた前日の総稽古でピアノの譜めくりをしただけで、ピエ=ヴィル邸の私的礼拝堂で行われた初演に列席しなかった。4人の著名なオペラ歌手──ソプラノのカルロッタ・マルキージオ(Carlotta Marchisio, 1835-1872)とその姉でコントラルトのバルバラ・マルキージオ(Barbara Marchisio, 1833-1919)、テノールのイタロ・ガルドーニ(Italo Gardoni, 1821-82)、バスのルイージ・アニェージ(Luigi Agnesi, 1833-1875. 本名ルイ・アニエLouis Agniez)──がソリスト、パリ音楽院の15人の学生が合唱を務めた初演の指揮は、作曲家ジュール・コーエン(Jules Cohen, 1835-1901)が執った。第一ピアノはかつてショパンに師事したパリ音楽院教授ジョルジュ・マティアス(George Mathias, 1826-1910)、第二ピアノはアンドレーア・ペルッツィ(Andrea Peruzzi)、ハルモニウムはトマの弟子で18歳のアルベール・ラヴィニャック(Albert Lavignac, 1846-1916)が担当した。
教皇庁の大使、作曲家マイアベーア、オベール、トマらが列席した初演は聴衆に深い感銘を与え、ただちに傑作と認められた。けれどもロッシーニは1年後の1865年4月24日に同じピエ=ヴィル邸で行った一度きりの再演を許しただけで楽譜を封印し、最晩年に作成した管弦楽編曲版の演奏も許さず、1868年11月13日パリ近郊パシーの邸宅で没したのだった。
近代和声を用い、複雑な転調を重ねる《小ミサ・ソレムニス》は、晩年のロッシーニがなお時代の先端をゆく作曲家だった証であるとともに、典礼ではなく私的な演奏を前提とした宗教音楽としても異彩を放っている。
《小ミサ・ソレムニス》の楽曲
ロッシーニの《小ミサ・ソレムニス》は、トレント公会議を経て1570年に定式化された盛儀ミサの通常文(下記
I~V)に器楽曲《宗教的前奏曲》と聖体賛歌《オー・サルタリス》を加えた12曲(N.1~12)からなる。
I キリエ[憐れみの賛歌]
N.1 キリエ「主よ、憐れみたまえ Kyrie eleison」
最弱音(pppp)で第一ピアノがスタッカートで弾く特徴的なリズムを伴奏に、4人のソリストと混声合唱がソッ
ト・ヴォーチェ(弱声)で祈りの言葉「主よ、憐れみたまえ」を和声的に繰り返す(イ短調、4分の4拍子、アンダ
ンテ・マエストーゾ)。歌の開始部はペルゴレージ《スタバト・マーテル》冒頭曲の着想を発展させたものと言え
る。ニデルメイエール《荘厳ミサ曲》の〈エト・インカルナトゥス〉を転用した〈キリスト、憐れみたまえ〉
(ハ短調、2分の2拍子、アンダンティーノ・モデラート)を挟み、〈主よ、憐れみたまえ〉をハ短調で繰り返してイ長
調に転じて終わる。
II グロリア[栄光の賛歌](次の6曲からなる)
N.2 グロリア「いと高きところ、神に栄光あれ Gloria in excelsis Deo」
三つの伴奏楽器による強奏の前奏に続いて4人のソリストと混声合唱が「いと高きところ、神に栄光あれ」と力
強く和す(ヘ長調、4分の4拍子、アレグロ・マエストーゾ)。バス独唱が先導する四重唱「地には善意の人々に(Et
in terra pax)」(4分の2拍子、アンダンティーノ・モッソ)を挟み、合唱がソット・ヴォーチェで「御身を讃美した
てまつる(Laudamus te)」と唱えて終わる。
N.3 グラティアス「御身に感謝し奉る Gratias agimus tibi」
ピアノ1台の伴奏による、コントラルト、テノール、バスの小三重唱曲(イ長調、4分の2拍子、アンダンテ・グラツ
ィオーゾ)。ソリストが旋律を転調しながらカノン風に歌い継ぎ、装飾的な変奏も交えて進行する。
N.4 ドミネ・デウス「主なる神 Domine Deus」
ピアノ1台で伴奏されるテノール独唱曲(ニ長調、4分の4拍子、アレグロ・ジュスト)。《スタバト・マーテル》(第
2稿、1842年)のアリア〈歎き憂い悲しめるその御魂は〉と同趣の楽曲でもカデンツァは無く、装飾的な要素を
廃して伸びやかに歌われる。後奏で転調し、ハ音の強打で次曲に移る。
N.5 クイ・トリス「世の罪をのぞきたもう者よ Qui tollis peccata mundi」
ピアノ1台とハルモニウム伴奏のソプラノとコントラルトの二重唱(ヘ短調、4分の4拍子、アンダンティーノ)。ピ
アノの前奏と伴奏がハープを模し、三度平行のハーモニーを基調とする訴求力の強い女声デュオが真摯に歌われ
る。ヘ長調に転じた後半部も基本的に同じ音楽で、後奏末尾の3小節で静かに閉じられる。
N.6 クオニアム「御身のみ聖にして Quoniam tu solus Sanctus」
ピアノ1台で伴奏されるバス独唱曲(イ長調、4分の4拍子、アレグロ・モデラート)。8分音符の刻みのリズムの長い
前奏を経て、バス独唱が朗々とした旋律でキリストを讃美する。その旋律は精妙に変化を遂げ、格調高く歌われ
る。
N.7 クム・サンクト・スピリトゥ「聖霊とともに Cum sancto Spiritu」
〈グロリア〉と同じ前奏をもつ開始部(ヘ長調、4分の4拍子、アレグロ・マエストーゾ)に続いて、2分の2拍子、ア
レグロの活力に富む合唱フーガとなる。「聖霊と共に」の主題に「アーメン」の対主題が絡み、2台のピアノがユ
ニゾンで奏するスタッカートの打音と後打ちのリズムがモダンな効果を醸し出す。末尾に〈グロリア〉の歌詞と
音楽を挟み、華やかな終結部で閉じられる。
III クレド[信仰宣言]
N.8 クレド「我は唯一の神を信ず Credo in unum Deum」
短い上向音型の前奏で力強く「クレド」と歌い出される第一セクション。4人のソリストも関与して第一ピアノ
を伴奏の要に転調を重ね、変ホ長調で終止する(ホ長調、4分の4拍子、アレグロ・クリスティアーノ[註:キリスト
教徒のアレグロを意味するロッシーニの造語])。
─ クルチフィクスス「十字架につけられ Crucifixus etiam pro nobis」
ソプラノ独唱、ハルモニウム、第一ピアノによる第二セクション(変イ長調、4分の4拍子、アンダンティーノ・ソス
テヌート)。減七和音や半音階の下向音階を織り交ぜた印象的なピアノの音型にハルモニウムが色彩を付与する。
旋律は一見平明ながら精妙に彫琢され、転調を重ねて推移する。
─ エト・レズレクシット「蘇りたもう Et resurrexit」
全員による第三セクション。合唱のソプラノ・パートに先導され、全員で力強く「蘇りたもう」と唱和する(ホ
長調、4分の4拍子、アレグロ)。四重唱を挟んで起伏に富む展開部を経て、「後の世の生命を(Et vitam venture
saeculi)」の主題と「アーメン」の対主題による二重フーガとなる(2分の2拍子、アレグロ)。最後に〈クレド〉冒
頭句「我は唯一の神を信ず」を力強く和して終わる。
器楽曲
N.9 宗教的前奏曲/奉献唱の間に Prélude religieux / pendant l'Offertoire
「老いの過ち」のピアノ曲集《藁ぶきの家のアルバム》から第2曲《宗教的前奏曲/奉献唱の間に Prelude
Religieux / Pendant L’Offertoire》を外して転用した楽曲。16小節の荘重な序奏(嬰ヘ短調、4分の4拍子、アンダ
ンテ・マエストーゾ)に続いてバッハ《音楽の捧げもの》の主題を変形させた主題のフーガとなる(4分の3拍子、
アンダンティーノ・モッソ)。複雑な転調を重ね、古風な中にもモダンな香りが漂う。終結部で変イ長調から嬰ヘ
長調に転じ、ハルモニウムのリトゥルネルが準備される。
IV サンクトゥス[感謝の賛歌]
N.10 サンクトゥス「聖なるかな Sanctus」
前曲を受けてハルモニウムが9小節のリトゥルネルを奏し、4人のソリストと混声合唱が無伴奏で「聖なるかな」
を歌う(ハ長調、8分の6拍子、[アンダンティーノ・モッソ])。静謐な曲調とソリストの力強い「いと高きところ、
ホザンナ Hosanna in excelsis」が強いコントラストをなし、最後に全員でこれを和して終わる。
賛歌
N.11 オー・サルタリス「おお、救いの犠牲よ O salutaris hostia」
ソプラノ独唱とピアノのための聖体賛歌[Inno eucaristico](ト長調、4分の3拍子、アンダンテ・モッソ)。「老いの
過ち」の《声楽曲の拾遺集》にあるコントラルトとピアノのための歌曲《田舎のオー・サルタリス O Salutaris,
de Campagne》をソプラノ用にホ長調からト長調に移調した挿入曲。
V アニュス・デイ[平和の賛歌]
N.12 アニュス・デイ「神の子羊 Agnus Dei」
コントラルト独唱と混声合唱による終曲(ホ短調、4分の4拍子、アンダンテ・ソステヌート)。第一ピアノの序奏の
途中からハルモニウムがppppで天上的色彩を添える。哀愁に富む独唱の旋律が単純な中にも深い感情を湛え、2
小節の無伴奏合唱によるソット・ヴォーチェの祈り「我らに平安を与えたまえ Dona nobis pacem」を挟んで高
揚する。序奏が回帰し、ホ長調の総奏で締め括られる。
《小ミサ・ソレムニス》の “不都合な真実”
解説に記したように、《小ミサ・ソレムニス》は友人の作曲家ニデルメイエールの死を悼んでロッシーニが作曲した私的なミサ曲である。自筆譜にはピエ=ヴィル伯爵夫人ルイーズへの献呈を記したタイトル頁とは別に、神に向けた二つの献辞が含まれる。一つ目のそれは、次のように書かれている。
四[声]部の小ミサ・ソレムニス、2台ピアノとハルモニウムの伴奏付き。パシーの私の保養地のために作
曲。演奏には、男、女、カストラートの三つの性による12人の歌手、すなわち合唱用に8人、独唱に4人の
合計12人のケルビム[智天使]がいれば充分です。神さま、次の比較を私にお許しください。12人はレオナ
ルド[ダ・ヴィンチ]によって『最後の晩餐』と呼ばれるフレスコに描かれた有名な宴会の12使徒と同じで
すが、あなたの信徒の中には間違った音を出す者もいるでしょう!! 主よ、ご安心ください、私の朝食には一
人のユダもいないと請け合います。そして私の歌手たちは、正しく、愛をこめて、あなたへの讃美を歌うこ
とでしょう。そしてこの小さな作品こそは、ああ、私の老いの最後の大罪なのです。
G.ロッシーニ パシー、1863年
この文言を真面目に受け取ることはできない。12人の歌手にカストラートを含めたのがその証左で、絶滅種というべき去勢した男性歌手は作曲と演奏の前提ではないからだ。歌手を12使徒と重ねてダ・ヴィンチの『最後の晩餐』に言及したのも戯言の域を出ず、これを真に受けて「12人の歌手のためのミサ曲」とするのは間違い。「小さな作品」と「最後の大罪」もロッシーニが好んだ対比の言葉遊びで、「老いの過ち Péchés de vieillesse」も「若気の過ち Péché de jeunesse」を逆手に取った自虐的なネーミングである。
次に、自筆譜の最後に書かれたもう一つの献辞を見てみよう。

= 神さま[Bon Dieu]=
これでこの貧しく小さなミサ曲が終わります。私が作曲したのは宗教音楽、それとも単にひどい音楽でしょうか? 私はオペラ・ブッファのために生まれました。それをあなたはよくご存知です! 少しの知識、僅かなハート、それがすべてです。祝福され、私を天国に受け入れてくれますように。
G. ロッシーニ パシー、1863年
ここでの「宗教音楽 la Musique Sacrée」と「ひどい音楽 la Sacrée musique」がダジャレであるのは明らかで、教会で演奏される宗教曲は駄作ばかり、との強烈な皮肉も見て取れる。「私はオペラ・ブッファのために生まれました。それをあなたはよくご存知です!」との言葉も《セビーリャの理髪師》だけが劇場のレパートリーに残り、代表作とされたことへの不満を込めた見せかけの卑下にすぎぬ。「少しの知識、僅かなハート、それがすべてです」も晩年の手紙に「競争相手のいない四流ピアニスト」と自称したのと同様の、謙遜を装った自信の裏返しと理解しうる。それでも「祝福され、私を天国に受け入れてくれますように」との願いはキリスト教徒としての本音と思われ、前の献辞でこの作品を大げさに「私の最後の大罪」としたことへの謝罪の意も込められている。
(みずたに あきら 日本ロッシーニ協会会長)
ロッシーニ《ミサ・ソレムニス(荘厳ミサ曲)》作品解説 水谷彰良
ミサ・ソレムニス(荘厳ミサ曲)Messe solenelle)管弦楽伴奏編曲
註《小ミサ・ソレムニス(Petite messe solennelle)》(1864年パリ初演)のロッシーニ自身による管弦楽伴奏改作(1866-68年成立)。
《ミサ・ソレムニス(荘厳ミサ曲)》の題名で初演されて流布したが、これはロッシーニの命名ではない。
初演 1869年2月28日パリ、イタリア劇場(サル・ヴァンタドゥール)
編成 4人のソリスト(ソプラノ、コントラルト、テノール、バス)、混声合唱、管弦楽(ピッコロ、2フルート、2オー
ボエ、2クラリネット、3ファゴット、4ホルン、2ピストン・コルネット、2ピストン・トランペット、4トランペッ
ト、3トロンボーン、オフィクレド、ティンパニ、4ハープ、オルガン、弦楽5部)
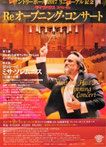
次に掲載するのは2017年9月1日サントリーホール リニューアル記念Reオープニング・コンサート ロッシーニ「ミサ・ソレムニス」のプログラムノート、水谷彰良「ロッシーニ《ミサソレムニス》」からの転載である(ロッシーニに関する前説を削除し、一部表記を変更)。

これは《小ミサ・ソレムニス》を大編成のオーケストラ伴奏に編曲したヴァージョンである。ロッシーニは「自分の死後、サクソフォーンの発明者サックスやベルリオーズが騒々しい編曲をすると困るから」との理由で1866~68年に改作し、400頁を超える総譜を遺して1868年11月13日パリ近郊パシーで没したのだった。
遺作となった管弦楽伴奏版の《小ミサ・ソレムニス》は、寡婦オランプから10万フランで用益権(演奏と出版に関する権利)を購入した興行師モーリス・ストラコシュにより1869年2月28日[註:従来の24日説は誤り]、パリのイタリア劇場(サル・ヴァンタドゥール)で初演され、3カ月後にはアメリカ初演されるなど世界各国で演奏が相次いだ。けれども、近代和声と複雑な転調を駆使してパレストリーナの様式とバッハ風のフーガを取り込み、ブルックナーやストラヴィンスキーを先取りする色彩的管弦楽法を用いた本作の意義は同時代に理解されず、イタリアでは「教会音楽としては世俗的すぎ、劇場音楽としてはあまりに退屈」と酷評され、すぐに忘れ去られた。再評価は1970年代に始まり、ロッシーニ財団の校訂譜(F.シピオーニ版)も1996年に成立したが、厳密な研究に基づくダヴィデ・ダオルミ校訂の全集版は2013年に出版され、今回の演奏がその日本初演となる。
ロッシーニが「私の老いの最後の大罪」と呼んだこのミサ曲は、音楽の巨匠が技術の粋を凝らし、彫琢した至高の音楽であり、神への私的な捧げものと理解しうる。だが、作品に込められたメッセージを読み取るのは難しい。今年3月に亡くなった指揮者アルベルト・ゼッダ氏が死の3か月前に語った、「ロッシーニの音楽は、死がすべての終わりではなく、未知の、より素晴らしい世界への通過点との期待を抱かせてくれる」との言葉が、隠された真実を解き明かしているように思えてならない。
《ミサ・ソレムニス》管弦楽伴奏版の楽曲
ロッシーニの《小ミサ・ソレムニス》は、トレント公会議を経て1570年に定式化された盛儀ミサの通常文(下記I~V)に
器楽曲《宗教的前奏曲》と聖体賛歌《オー・サルタリス》を加えた12曲(N.1~12)からなる。
I キリエ[憐れみの賛歌]
N.1 キリエ「主、憐れみたまえ」
弱音(ppp)でファゴットと低弦楽器がスタッカートで奏する特徴的なリズムを伴奏に、ソリスト4人と混声合唱
が弱声(ソット・ヴォーチェ)で「主、憐れみたまえ」と繰り返す(イ短調、4分の4拍子、アンダンテ・マエストー
ゾ)。中間部「キリスト、憐れみたまえ」はニデルメイエール作曲の無伴奏合唱曲を借用し、弱声とレガートで
歌われる。「キリエ」をハ短調で繰り返し、イ長調に転じて終わる。
II グロリア[栄光の賛歌]
N.2 グロリア「いと高きところには神に栄光あれ」
全楽器が強奏する前奏に続いて、ソリスト4人と混声合唱が「いと高きところには神に栄光あれ」と力強く和す
(ヘ長調、4分の4拍子、アレグロ・モデラート)。バス独唱が先導する四重唱「地には善意の人々に」を挟み、合唱
が弱声で「おんみを讃美したてまつる」と唱える。
N.3 グラティアス「われらおんみに感謝したてまつる」
ファンファーレの先導する前奏を持つ、コントラルト、テノール、バスの三重唱曲(イ長調、4分の2拍子、アンダ
ンテ・グラツィオーゾ)。主旋律を転調しながらカノン風に歌い、装飾的な変奏も交えて進行する。
N.4 ドミネ・デウス「主なる神」
テノール独唱曲(ニ長調、4分の4拍子、アレグロ・ジュスト)。《スタバト・マーテル》のテノールのアリア「歎き
憂い悲しめるその御魂は」と同じリズムによる楽曲だが、カデンツァはなく、装飾的要素を退けて伸びやかに歌
われる。後奏で転調し、次曲に移る。
N.5 クイ・トリス「世の罪をのぞきたもうものよ」
4台のハープを伴奏の要とするソプラノとコントラルトの二重唱(ヘ短調、4分の4拍子、アンダンティーノ)。三度
平行のハーモニーで歌い始め、「ミゼレーレ・ノビス(われらを憐れみたまえ)」の繰り返しが強い訴求力を持つ。
ヘ長調に転じた後半部も基本的に同じ音楽で、トリルを伴う短いカデンツァで歌が閉じられる。
N.6 クオニアム「おんみのみ聖にして」
バス独唱曲(イ長調、4分の4拍子、アダージョ~アレグロ・モデラート)。8分音符の刻みのリズムによる前奏を経
て、バス独唱が朗々とキリストを讃美する。その旋律は精妙に変化を遂げ、大河の如く滔々と流れる。
N.7 クム・サンクト・スピリトゥ「精霊とともにありて」
「グロリア」と同じ前奏と開始部に続いて活力に富む合唱フーガが歌われる(ヘ長調、2分の2拍子、アレグロ・ア・
カペッラ)。「クム・サンクト・スピリトゥ」の主題に「アーメン」の対主題が絡み、後打ちのリズムと弦楽器の
スタッカートがスイングする感覚を醸し出す。末尾に「グロリア」開始部の音楽を挟み、終結部となる。
III クレド[信仰宣言]
N.8 クレド「われは唯一の神を信ず」
短い上向音型の前奏で力強く「クレド」と歌い出す合唱曲(ホ長調、4分の4拍子、アレグロ・クリスティアーノ
註)。ソリスト4人も関与し、転調を重ねて高揚する。 註:「キリスト教徒のアレグロ」を意味するロッシーニの造語。
─ クルチフィクスス「十字架につけられ」
ソプラノ独唱曲(変イ長調、4分の4拍子、アンダンティーノ・ソステヌート)。減七和音や半音階の下向音階を織り
交ぜた木管楽器と弦楽器のたおやかな伴奏を伴い、歌の旋律も転調しながら進行する。
─ エト・レズレクシット「よみがえりたもう」
合唱のソプラノ・パートに先導され、全員で力強く「よみがえりたもう」と唱和する(ホ長調、4分の4拍子、プリ
モ・テンポ[アレグロ])。四重唱の関与と起伏に富む展開部を経て、「後の世の生命を」の主題と「アーメン」の
対主題による合唱フーガが歌われる(2分の2拍子、アレグロ・ブリランテ)。「クレド」冒頭句(われは唯一の神を信
ず)を全員で力強く唱和して終わる。
器楽曲:
N.9 宗教的前奏曲/奉納唱の間に
低音木管楽器、3本のトロンボーン、オフィクレド、オルガンが強奏する序奏に続いて、オルガンが単独にフー
ガを奏する(4分の3拍子、アンダンティーノ・モッソ)。主題はバッハ《音楽の捧げもの》の主題の変形に当たる
が、複雑な和声と転調を取り入れ、序奏と同じ編成の強奏で締め括る。
IV サンクトゥス[感謝の賛歌]
[10] サンクトゥス「聖なるかな」
前曲を受けてオルガンが9小節のリトゥルネルを奏し、ソリスト4人と混声合唱が無伴奏で「サンクトゥス」を歌
う(ハ長調、8分の6拍子、[アンダンティーノ・モッソ])。静謐な曲調とソリスト4人の力強い「いと高きところにホ
ザンナ」が強いコントラストをなす。
賛歌:
N.11 オー・サルタリス「おお、救いの犠牲」
ソプラノ独唱による聖体賛歌(ト長調、4分の3拍子、アンダンテ・ソステヌート)。「老いの過ち」のコントラルト
とピアノのための歌曲《田舎のオー・サルタリス》をソプラノと弦楽合奏に編曲して挿入された。
V アニュス・デイ[平和の賛歌]
N.12 アニュス・デイ「神の子羊」
コントラルト独唱、混声合唱と管弦楽による終曲(ホ短調、4分の4拍子、アンダンテ・ソステヌート)。木管楽器の
短い序奏とすすり泣くような弦の前奏に導かれ、コントラルト独唱が深い感情を湛えて「世の罪をのぞきたもう
神の子羊」と歌い始める。2小節の無伴奏合唱の祈り「われらに平安を与えたまえ」を挟んで高揚し、序奏の回
帰を経てホ長調の総奏で閉じられる。
(みずたに あきら 日本ロッシーニ協会会長)
・小ミサ・ソレムニス(Petite Messe solennelle)作品解説
↑
日本ロッシーニ協会紀要『ロッシニアーナ』第38号(2018年6月発行)に掲載したオリジナル編成と管弦楽伴奏版の最も詳
しい作品解説──水谷彰良「ロッシーニ全作品事典 (37)《小ミサ・ソレムニス》」──はこれをクリックしてご覧ください。
(2021年10月改訂)